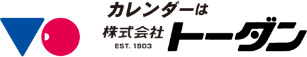こよみの雑学
こよみの雑学
カレンダーや暦の雑学をご紹介します。

「暦(こよみ)」の語源
「こよみ」の語源は「かよみ」。「か」とは、2日(ふつか)、3日(みっか)、4日(よっか)というときの「か」で、日の意味です。それから「よみ」とは、数えること。つまり、日を数えること「かよみ」から「暦(こよみ)」に変化したものといわれています。 漢字の「暦(こよみ)」は、歴史の「歴」と同じ意味を持っていて、どちらも日を数えることを表わしています。
「カレンダー」の語源
その答えは古代ローマにかくされています。古代ローマでは、夕方、月がはじめて見えると「月がみえたぞ!」と呼んで人々に知らせる習慣がありました。その「呼ぶ」をギリシャ語では「カロ」と言い、そこから月初めを意味する「カレンヅ」とか、「カレンダエ」という言葉が生まれ、「カレンダー」の語源となったと考えられています。 古代ローマの暦(こよみ)がヨーロッパ各地で使われたため、「カレンダー」は各国語で同じ様な名前になりました。

欧米では、9月の事を「7番目の月」と呼ぶ。
例えば英語でいうセプテンバー(9月)って、何となくセブン(7)と似てると思いませんか?ラテン系の言葉だと、よりはっきりと9月は「7番目の月」、10月は「8番目の月」と言っています。 これは、ローマ皇帝シーザーが、政治家の任期に合わせ、新年を3月として2ヶ月繰上げた結果、7番目の月は実際には9月、8番目の月は10月‥となりました。なんともややこしいですね。
毎月の日数はどうやってできたの?
現在の月ごとの日数は古代ローマの制度をそのまま引継いでいます。古代ローマでは3月が新年で、そこから大の月(31日)と小の月(30日)が交互になって、年末の2月だけが29日でした。 ある時、シーザー(ユリウス・カエザル)の後継者となったアウグストゥス皇帝を称えて、ローマの元老院が、それまでシクストゥス(6番目の月という意味)と呼ばれていた今の8月を、アウグスツスと改名しました。その時に小の月だった8月を大の月に変更しました。そして調整のために、2月を28日にしたのです。その上、9月から12月の大小の順番を逆にした結果、今日のような月ごとの日数になりました。
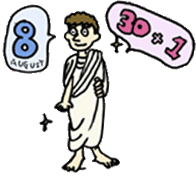
1週間のはじまりは何曜日?
日曜日からです。実は私たちが使っている7日間の週は、古代ユダヤ人の習慣に由来しています。この世のはじめ、神様が6日間で天地の万物を創造し、最後に人類の祖アダムを自分の分身として創り、7日目はお休みにしました(安息)。この日(安息日=サバット)は、私たちの暦では土曜日にあたります。だから1週間は、日曜日にはじまり、土曜日に終わる。 このことは『旧約聖書』の「創世記」に書かれています。ユダヤの習慣を受け継いだキリスト教では、安息日の前日(金曜日)に処刑されたキリストが、安息日の翌日(日曜日)に復活したことを重視して、週のはじめでもある日曜日を祝いの日としました。 欧米では土曜日のことを「サバット」とも「ウィークエンド」とも呼んでいます。
日本の暦(こよみ)はいつはじまったの?
はるか昔、原始時代には自然の移り変りに従って狩猟や農耕が行われていたので、山の残雪の形や、季節を知らせる花などが、そのまま暦の役割をしていました。 有名な『魏志倭人伝』(ぎしわじんでん)には、3世紀頃の日本人について「きちんとした暦の知識を持っていないが、農耕のための自然暦を使っている」という意味のことが書かれています。 日本に正確な暦が百済(くだら・朝鮮半島西南部)から伝えられたのは、6世紀中頃のことだそうです。
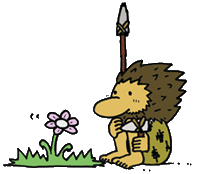
日本で今の暦(新暦)を使い始めたのはいつ?
日本では、長い間「旧暦(太陰太陽暦)」を使っていました。それが幕末に開港し、欧米諸国との交際が再開。暦(こよみ)が違うと不便なだけじゃなく、未開国として遅れをとってしまうかも知れんません。そこで欧米と同じ太陽暦を採用する必要が出てきました。
さて、改暦のきっかけとなったのは、明治6年(1873年)6月に閏月があり、その年は1年が13ヶ月になるはずでした。1年に13回も月給を支払うのは大変!ということで、明治5年の年末にあわてて改暦し、欧米と同じ太陽暦(新暦)を取り入れました。 突然の改暦に、人々は驚いたでしょうね。その後、長い年月をかけて今の暦は普及していきました。
十二支に猫?
十二支はもともと中国でつくられ、漢字文化とともに東アジアの国々に広まりました。朝鮮や日本では1500年以上も古くから使っていて、当時ジンギスカンの建国したモンゴル帝国でも十二支を使っていたため、ロシアやヨーロッパの一部にまで普及しました。近年では、中国・韓国・ベトナムなど、東アジア系の人々が世界中に商業活動を展開したり、移住したりしているのでより広く普及しています。ベトナムでは5番目の「卯(うさぎ)」の代わりに猫が入っていたり、他にも亥(いのしし)が豚だったり、寅(とら)が豹だったり、起源は同じでもお国柄で少しずつ違っています。
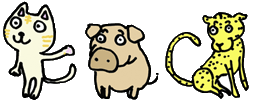
教えて和風月名!
和風月名とか、昔の月名とか、月の異称(いしょう)と呼ばれるものは、次の通りです。
1月 睦月(むつき) 人々が集って睦び合う
2月 如月(きさらぎ) 衣更着と書き、更に重ね着をするという説と、春用に薄着に変わるという説がある
3月 弥生(やよい) 植物が生い茂る
4月 卯月(うづき) 卯の花(うつぎの花)が咲く
5月 皐月(さつき) 早苗を植える
6月 水無月(みなづき) 水が涸れる、または水の豊富なこと
7月 文月(ふみづき) 七夕に文筆の上達を祈る
8月 葉月(はづき) 葉が落ち始める
9月 長月(ながつき) 夜が長くなる
10月 神無月(かんなづき) 神々が出雲に集まる、または、神祭りが多い
11月 霜月(しもつき) 霜が降りる
12月 師走(しわす) 師も走り廻る、物事を仕終わる
10月は神様がお留守?
10月の和風月名は「神無月」といいます。それは文字の通り神様が不在になるからだと言われています。
では神様はどこへ行ってしまうのでしょうか?
実は、全国八百万(やおよろず) の神様は、島根県にある出雲大社に集まるといわれています。そのため出雲だけは10月の事を「神在月(かみありづき)」といい、神様を迎えるためにさまざまな神事が行われています。
ちなみに神様みんなが出雲に出掛けても、ちゃんと留守番をしてくれている神様がいます。一般的なのは、右手に釣竿、左手に鯛を抱えた恵比寿様が留守番役。この時期に「えびす講」という行事を行う地域も多いのです。
西向く侍(さむらい)
「西向く侍」って聞いたことありますか?太陽暦には大の月(31日で終わる月)と小の月(30日で終わる月)があって、「西向く侍」は小の月の二・四・六・九・十一月を指しています。覚えやすいように「にしむくさむらい」と読んだんですね。ちなみに漢字の十一は縦に重ねると「士(さむらい)」という字に似ているから、十一月のことを洒落て「侍」といいます。 新暦と違って旧暦の場合は、その年によって大小の月の配列が変わってしまうのですが、江戸時代、ある年の小の月(旧暦では29日)の組合せが二・四・六・九・十一月だったときにこの言い方ができました。太陽暦になった時、この言葉を思い出して再利用したわけですね。

2月29日生まれの人の誕生日は4年に一度だけ?
閏年の2月29日に生まれた人は4年に1度しか誕生日がまわってこないから、100年たっても25歳なのでしょうか?もちろん法律上はそんなことなく、お役所に2月29日の出産届を持って行けば、戸籍にはそのとおり「2月29日生れ」と記載されますが、満年齢などの計算では、3月1日生まれと同じ扱いになります。つまり事実上は3月1日の誕生と考えればいいのですね。
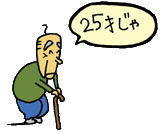
日本の正式な暦はどこで発行しているの?
国立天文台(東京都三鷹市)で編集した暦が日本国の正式の暦です。翌年の主要な内容(平年・閏年の別、二十四節気、雑節、日曜表、10日ごとの東京での日の出、日の入り、日食や月食など)が、2月1日付の『官報』で発表されています。 国立天文台では毎日の日の出入まで記載された『暦象年表』を作製していますが、これは一般には頒布されていません。 ただし、同じ内容は同年11月に丸善出版から発行される『理科年表』の「暦部」に掲載されています。