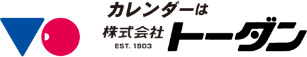日本の祝日
こよみの基礎知識
日本の祝日
国民の祝日について
「国民の祝日」とは、戦前の祝祭日*を廃止して、日本国憲法のもとに新しく制定された日本国民の祝日のことです。昭和23年(1948年)7月に「国民の祝日に関する法律」が制定され、その後に何度か改正が行われ、現在の祝日となっています。 この法律の第1条では、「よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、祝い、感謝し、記念する日を定める」という内容がうたわれています。
*祝祭日とは、戦前に行われいてた「祝日」と「大祭日」を併称したもので、正式には「祝日大祭日」と言います。当時「祭日」には「皇室の祭典が行われる日」との意味がありましたが、戦後新たに制定された「国民の祝日に関する法律」には、「祭日」という言葉は表記されていません。

振替休日
祝日が日曜と重なった場合、その後の最も近い祝日ではない日を休日にする制度です。 昭和48年(1973年)に「国民の祝日に関する法律」に追加され、平成17年(2005年)に改正されました。
国民の休日
「国民の休日」とは、祝日と祝日に挟まれた真ん中の日を休日とするもので、昭和60年(1985年)に「国民の祝日に関する法律(祝日法)」に追加されました。「国民の休日」とは通称であり、祝日法ではただ「休日」と呼んでいます。
元々は、憲法記念日(5月3日)とこどもの日(5月5日)の中日(平日)であった5月4日を休日とし国民に長期休暇(ゴールデンウィーク)を与える目的で制定されたものですが、平成19年(2007年)から5月4日が「みどりの日」という祝日となったことから、耳にする機会が減った名称となりました。ただハッピーマンデー制度により平成15年(2003年)以降「敬老の日」が9月の第3月曜日となったことから、「国民の休日」が数年から数十年に一度現れるようになりました。
祝日一覧 (2025年1月現在)
元日
1月1日
「年のはじめを祝う。」が法定の趣旨です。 元日は1月1日のことで、昔は「がんにち」と読みました。元日の朝を特に「元旦(がんたん)」「歳旦(さいたん)」などと呼んで、1年のはじまりを祝います。元日の由来は、宮中の年中行事だった元日(がんじつ)の節会(せちえ)と言われていますが、正月は一般の人にとっても年神が来るのを祝う大切な行事でした。初詣に行ったり、晴れ着で屠蘇(とそ)をいただいたり、お節料理やお雑煮でお祝いをします。
成人の日
1月の第2月曜日
「おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。」が法定の趣旨です。 成人を祝うしきたりは昔からあります。社会を構成する一員になったことを認知する通過儀礼といえるでしょう。
建国記念の日
2月11日
「建国をしのび、国を愛する心を養う。」が法定の趣旨です。 かつては「紀元節」と言われていました。神武天皇即位の第一日、つまり皇紀元年1月1日が太陽暦の2月11日にあたるからです。戦後、「紀元節」という祝日は消えましたが、「建国記念の日」を制定する際に、この日が選ばれました。「建国の日」ではなく、「建国を記念する日」という考えに立っています。
天皇誕生日
2月23日
「天皇の誕生日を祝う。」が法定の趣旨です。 全国民の統合の象徴としての天皇の誕生を祝う日となっています。この日、皇居では各省大臣を招いての宴会や、各国大使を招いての茶会が開かれます。また、皇居の二重橋の門が開放されて国民の一般参賀が行われるなど、さまざまな祝賀行事が行われます。
春分の日
春分日(3月21日頃)
「自然をたたえ、生物をいつくしむ。」が法定の趣旨です。 春分は二十四節気のひとつです。春分の前後各3日間、計7日間を春の彼岸といい、春分の日は中日となります。太陽が春分点を通過する日で、真東から出て真西に沈みます。昼夜の長さがほぼ等しくなり、この日を境にだんだん昼間が長くなります。
昭和の日
4月29日
「激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。」が法定の趣旨です。 4月29日は昭和天皇の誕生日で、平成になった当初からこの日を「昭和の日」とする案はありましたが、社会情勢などから「みどりの日」という名称になりました。その後、「昭和の日」に改正しようという運動が起こり、2度の廃案を経て平成17年(2005年)の祝日法改正で成立しました。
憲法記念日
5月3日
「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。」が法定の趣旨です。 昭和21年(1946年)11月3日に公布された新憲法が、半年の準備期間をおいて翌昭和22年(1947年)に施行された日です。日本国憲法は主権在民・戦争放棄・基本的人権の尊重などを骨子とした、他に類をみない平和憲法となっています。
みどりの日
5月4日
「自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。」が法定の趣旨です。 もともとは在位64年の歴代最長となった昭和天皇の誕生日(4月29日)の名称でした。平成19年(2007年)から4月29日が「昭和の日」と改正されるのに伴い、5月3日の「憲法記念日」と5月5日の「こどもの日」という祝日に挟まれる平日で「国民の休日」であった5月4日の祝日名として残されました。
こどもの日
5月5日
「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。」が法定の趣旨です。 児童福祉法が昭和22年(1947年)に制定され、昭和26年(1951年)5月5日に児童憲章が定められました。こどもの日は昭和23年(1948年)に制定されています。この日は端午の節句でもあり、男の子のお祝いをする日でもあります。
海の日
7月の第3月曜日
「海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。」が法定の趣旨です。 もともとは、明治9年(1876年)に明治天皇が東北地方巡幸の際、それまでの軍艦ではなく、灯台巡視の汽船「明治丸」で航海をして7月20日に横浜港へ帰着したことに由来しています。祝日法改正により平成15年(2003年)から7月の第3月曜日となりました。
山の日
8月11日
「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。」が法定の趣旨です。 夏休み、お盆休みの時期に連動させることでより多くの人が山や自然と触れ合える日となることを目的に、平成26年(2014年)に制定されました。
敬老の日
9月の第3月曜日
「多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。」が法定の趣旨です。 もともとは、聖徳太子が四天王寺(大阪市)に悲田院(貧窮者・病者・孤児などを救うための施設)を設立した日にちなんで9月15日に制定されていましたが、祝日法改正により平成15年(2003年)から9月の第3月曜日となりました。
秋分の日
秋分日(9月23日頃)
「祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。」が法定の趣旨です。 秋分は二十四節気のひとつです。秋分の前後各3日間、計7日間を秋の彼岸といい、秋分の日は中日となります。太陽が秋分点を通過する日で、真東から出て真西に沈みます。昼夜の長さがほぼ等しくなり、この日を境にだんだん昼間が短くなっていきます。
スポーツの日
10月の第2月曜日
「スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。」が法定の趣旨です。 東京オリンピックの開会式が昭和39年(1964年)10月10日だったのを記念して、昭和41年(1966年)に「体育の日」として制定されました。祝日法改正により、平成12年(2000年)から10月の第2月曜日となり、令和2年(2020年)から「スポーツの日」に名称が変更されました。史上初めてカタカナが使われた祝日名となりました。
文化の日
11月3日
「自由と平和を愛し、文化をすすめる。」が法定の趣旨です。 戦前は「明治節」といい、明治時代の天長節(明治天皇の誕生日)であった祝祭日でした。それとは無関係でしたが、昭和21年(1946年)のこの日に、主権在民・戦争放棄・基本的人権の尊重を宣言して平和と文化を強調した新憲法が公布されたので、これを記念して「文化の日」としました。全国的に晴天の多い気象上の特異日としても有名です。
勤労感謝の日
11月23日
「勤労をたっとび、生産を祝い、国民がたがいに感謝しあう。」が法定の趣旨です。 昭和23年(1948年)に制定されたこの祝日は、戦前は「新嘗祭(にいなめさい)」と称していました。天皇が新穀を天神地祗(ちぎ)に勧め、自らも新穀を食するという皇室の祭祀であったことから、現在でも農業関係者による祭典という色彩が強く、この日を中心にして「農林水産祭」が行われています。