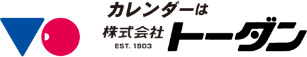暦注
こよみの基礎知識
暦注(れきちゅう)
昔の暦は一冊の本でした。日付だけではなく、毎日その日の吉凶を決める様々な注記事項が、ぎっしりと記載されていました。それらの、日の吉凶に関する記載事項を暦注といいます。その日が吉か凶か、何をしてはいけない日か、何をしたらいい日かをあらわします。 昔の人々にとっては、この暦注が生活のひとつの行動基準でした。ただし暦注の種類は数多く、それぞれのルールで暦日に配当されているので、同日に吉凶が矛盾する場合も少なくありません。吉凶はひとつの誡めだと受け止めればよいのではないでしょうか。
暦注一覧
六曜(ろくよう)
現在では、暦のお日柄、すなわち暦注といえば「六曜」が主役です。「六輝(ろっき)」(あるいは「六曜星」「六輝星」)とも呼ばれています。六曜自体の起源はよく分かっていませんが、もともとは中国で行なわれていた「六壬時課(りくじんじか)」と呼ばれる時刻占いの一種でした。 これは一日を12刻に分け、ある日の最初の一刻を大安、次の一刻を留連、次を速喜、次を赤口、次を小吉、最後を空亡とするもので、その次の日は、第一刻を留連から始めるというものです。 この六壬時課が日本の室町時代に伝えられ、江戸時代後半になって日の占いに変化し、名称や順序も次第に今日の先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口となりました。 香港などで売られている暦には、今でも六壬時課が掲載されているものがあります。
九星(きゅうせい)
九星とは、人間の運勢や吉凶の判断に用いられる九つの星のことです。一白(いっぱく)、二黒(じこく)、三碧(さんぺき)、四緑(しろく)、五黄(ごおう)、六白(ろっぱく)、七赤(しちせき)、八白(はっぱく)、九紫(きゅうし)の9つからなりますが、現実の天体の星とは関係ありません。また、他の暦注のように、万人に等しくその日のお日柄や吉凶を教えるものではなく、一人一人の生年月日によって吉凶が別々になるという特長があります。つまり、九星をみる場合は、まず自分が何の星かを知らなければなりません。西洋の星占いと同じ性質のものです。 一から九までの数字に、白、黒、碧、緑、黄、赤、紫の7色と、木、火、土、金、水の五行を配当したものが各人の星である九星(本命星ともいう)です。九星による吉凶判断は近年盛んですが江戸時代までの暦本に九星は記載されず、明治以降に暦や本に記載されるようになりました。こういうところから九星の基本的なルールが実は決まっておらず、暦本によって記載内容に異同があります。
十干、十二支、十干十二支
十干(じっかん)は、もともと日の順序を示すための符号だったと考えられ、十二支は初め12ヶ月の順序を示すための符号であったとされています。
十干も十二支も、初めはそれぞれ別に用いられていたものですが、中国の殷(いん)王朝時代の頃から、この十と十二が組み合わされて、その最小公倍数である「60」の周期で年、月、日を数えるのに用いられました。
十二直(じゅうにちょく)
十二直は日々の吉凶を見るためのもので、日本で最も古く飛鳥時代から用いられていた暦注です。一昔前までは六曜以上に信じられ、日々の吉凶を見る上で最も重視されていました。 建・除・満・平・定・執・破・危・成・収・開・閉のことですが、もともとは北斗七星の柄の方位からきたものです。古代中国では、北極星を中心に一日一回転する北斗七星が12等分されて、時刻、日、季節を判別するのに用いられていました。それが発展して十二直という日々の吉凶を占うものになったのです。現在でも利用している人は一定数いるようです。
二十八宿(にじゅうはっしゅく)
二十八宿とは、太陽が天球上を運行する黄道上にそって一周天を28の星座に分割したもので、もとは古代中国の星座です。月の天球上の位置を示すために用いられた、純天文学的なものでした。それが中国からインドに渡り日の吉凶を知るために用いられ、唐時代には七曜と共に「宿曜」として中国に逆輸入され、やがて日本にもたらされました。
八世紀初頭の貴人の墓と言われる高松塚古墳内の天井に二十八宿の諸星が描かれており、かなり以前から日本に伝えられていたとも推定されます。
なお、二十八宿は、中国からインドに渡った際に二十七宿となり、日本でもそのまま使用されていましたが、貞享の改暦(1685年)以降は二十八宿が用いられるようになりました。
三りんぼう
大安・友引などの六曜とともに、現在でも民間に根強く生きている暦注です。「三隣亡」という文字から、この日に棟上げ・建築を行うと三軒隣まで焼き滅ぼすと言われます。しかし江戸時代の古い雑書などには「三輪宝」と記されており、「屋立てよし」「蔵立てよし」と注記してあるので、もともとはめでたい日であったものが、いつ頃からか悪い日に変わっていったと考えられます。このようにもともと由緒のはっきりしない暦注ですが、六曜とともに幕末に庶民の間で次第に流行していき、現在でもまだ多くのカレンダーに記載されています。
七曜(しちよう)
七曜とは、七つの星である日(太陽)、月(太陰)、木星、火星、土星、金星、水星の総称で、これを用いて吉凶を占うことです。今日ではこの七曜名を暦に用い、一週間に割り当てた曜日名として日常生活に欠かせないものとなっています。
日本に7日の週日が伝えられたのは意外に古く、平安時代のはじめの大同元年(806年)に弘法大師空海が唐から帰国した際、『宿曜経』を持ち帰ったことによります。
このお経には「二十八宿」と「七曜」の組合せによって、人の運勢を占う術が書いてありました。つまり、一種の占星術で、この宿曜術(宿曜道)は平安時代から鎌倉時代にかけて貴族達の間で流行し、 日(密・蜜とも書かれました)・月・火・水・木・金・土は、平安時代以降の暦に必ず記載されました。 興味深いことに、日本の暦に書かれた曜日と、当時ヨーロッパで使用されていた曜日とが1日も食い違うことがなく、千年以上も続きました。