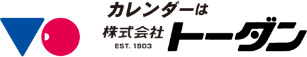十干 十二支 十干十二支
こよみの基礎知識
十干、十二支、十干十二支
十干(じっかん)
十干とは甲(こう、きのえ)・乙(おつ、きのと)・丙(へい、ひのえ)・丁(てい、ひのと)・戊(ぼ、つちのえ)・己(き、つちのと)・庚(こう、かのえ)・辛(しん、かのと)・壬(じん、みずのえ)・癸(き、みずのと)の総称で、もともとは日の順序を示すための符号だったと考えられています。1ヶ月を上旬・中旬・下旬の3つに分けた場合の、一旬(十日間)の一日一日を示す数詞でした。第一日目を甲、二日目を乙…と数えていくために用いられていたわけです。十という数字は物事を分割するのに都合が良いので、十干は大変便利だったことでしょう。
十二支(じゅうにし)
子(し)・丑(ちゅう)・寅(いん)・・・という十二支は、今から三千年以上も昔の中国の殷(いん)王朝の時代に、すでに用いられていたとも言われています。初め十二支は12ヶ月の順序を示すための符号であり、また1,2,3・・・という数字を使うのと同じように、物ごとを分類するときの記号として使われ、動物を表すものではありませんでした。数百年の後に、子、丑、寅・・・では覚えにくいため、子を鼠(ねずみ)、丑を牛、寅を虎にあてはめるようになったのです。 十二支の古い書体を見ると、卯と兎の耳、巳と蛇のとぐろを巻いた姿など、かたちが似ているものもあります。
| し | ちゅう | いん | ぼう | しん | し | ご | び | しん | ゆう | じゅつ | がい |
| 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ね | うし | とら | う | たつ | み | うま | ひつじ | さる | とり | いぬ | い |
いぬの日:安産祈願は「いぬ」の日に!
安産祈願に良い日があるのをご存知でしたか? 赤ちゃんを授かるお母さん、お父さん、そしてご家族の方、安産祈願のお参りをする前に「戌(いぬ)の日」をチェック!
「いぬ=安産」
1ヶ月にほぼ3回ある、「いぬの日」。 この日には全国のいろいろな神社で安産祈願が行われます。 さて、なぜ"いぬ"なんでしょうか? そのワケは、いぬのお産が軽いのにあやかっているからなんです。 他にも、生まれてくる赤ちゃんを魔物から護ってくれるという願いもあるようです。
「安産の味方、岩田帯」
そんな「いぬの日」に行う儀礼で、妊娠5ヶ月目のお母さんが帯をおなかに締め、赤ちゃんの成長と安産をお祈りする「帯祝い」 と呼ばれるものがあります。 そのときに使う帯を「岩田帯」といい、紅白の帯や白木綿の帯を用います。地方によってさまざまな帯があり、帯に「戌(いぬ)」 や「寿」の字を書くところもあるようです。 安産祈願で有名な「水天宮」では、社殿の前にかかる鈴を鳴らす紐を使った岩田帯や「鈴乃緒(すずのお)」という変わった帯もあります。 いろいろな形がある安産祈願ですが、生まれてくる赤ちゃんやお母さんのことを大切にする想いはみんな一緒なんですね。
みの日:「み」の日は弁財天の縁日
金運といえばヘビがよく登場します。ヘビは弁財天のお使いだからで、「み」の日は干支でいうヘビの日。弁財天とゆかりのある「み」の日は財福にご利益があります。
「河の神から財の神に」
弁財天は元々インドの河の女神です。本来は「弁才天」でしたが、江戸時代に七福神巡りが流行し、 銭洗弁天の信仰が盛んに行われたことで変化が現れます。"才"が"財"に変わり、財宝を授ける「弁財天」と表すようになりました。 一ヶ月にほぼ3回ある「み」の日の「み(巳)」は干支でヘビを表すので、弁財天の縁日になっていきました。近くに弁財天を奉っている神社があれば、この日に財福を授かりに行ってはいかがでしょうか?
「みの日にまつわるフシギな話」
"お金を洗うと増える"ことで有名な「銭洗弁天(宇賀福神社)」では、源頼朝が「巳の年、巳の月、巳の日」の夜に見た夢のお告げから、この場所で霊水を見つけ、それを奉り創建されたといわれているそうです。
初午:「はつうま」は一年で最もラッキーな日
2月には初午(はつうま)と呼ばれる一年で最も運気が高まると言われている日があります。
初午は2月の最初の午の日にあたります。この日、全国の稲荷神社では、お祭りが行われます。 狐の像がある神社を近所で見かけたことはありませんか?それが稲荷神社です。
初午に稲荷神社で祈願をすると、様々なご利益が得られるとされています。なぜなら、稲荷神社には開運招福・商売繁盛・受験合格をつかさどる稲荷大神がまつられているからです。稲荷神社は日本全国に数多くあるので、受験生や商売繁盛を祈願したい方は、 近所で探してみてはいかがでしょうか。
十干十二支(じっかんじゅうにし)/干支(えと)
十干も十二支も、はじめは別々に用いられていたものですが、中国の殷の頃から、この十と十二が組み合わされて、その最小公倍数である「60」の周期で年、月、日を数えるのに用いられました。
十干と十二支を組み合わせると甲子から癸亥まで60個の干支ができます。これを、干支・十干十二支・六十干支・六十花甲子、「えと」あるいは甲子(かっし)と呼んでいます。 歴史的には、干支は日よりも年に対して重要でした。
よく知られているところでは、天武天皇即位の際の内乱は、その年の干支をとって「壬申(じんしん)の乱」(672年)と呼ばれますし、明治維新の際の戦乱は「戊辰(ぼしん)の役」(1868年)と呼ばれるように、干支は使われてきました。
かのえさる:眠ってしまうと三尸の蟲が?
60日に一度の庚申(かのえさる)の日。その日の夜、あなたの身体から蟲(むし)が抜け出すんです…。 その蟲が外に出ると人の寿命を縮めると言われるのだから、さあ大変。人々はなんとか策を考えて「寝ない」ことにしました。 それが「庚申待ち(こうしんまち)」のはじまりです。
「庚申の日、徹夜の攻防戦」
60日に一度「庚申」の日がやってきます。 中国の道教によれば、この日に眠ってしまうと身体の中から「三尸」という蟲が抜け出してしまいます。 三尸は身体を抜け出すと天帝にその人の悪事を告げて、なんと寿命を縮めてしまうのです。 そこでこの蟲を外に出すまいと、人々は庚申の日に神々を祭り酒盛りなどをして過ごす、夜通しのお祭りごとを始めました。 これが「庚申待ち」と呼ばれる帝釈天のお祭りです。
「三尸を倒したしるし」
さて、そんな恐ろしい三尸ですが、実は三年間体に留めておけば死んでしまうと言われています。そこで、三年間欠かさず庚申待ちをやり遂げたときには「庚申塔」や「庚申塚」を建立したそうです。これには「みざる、いわざる、きかざる」の三匹のサルが彫られたり、庚申待ちを行った村の名前や人の名前が彫られたりいろいろなものが現存します。 あなたの町にもお祭りの名残が残っているかも?
きのえね:甲子園の”甲子”のひみつ
高校野球といえば、阪神甲子園球場。 実は、甲子園の"甲子"という名前には意味があります。その答えは、この球場が誕生した年にあったんです。
「甲子」の正体
甲子は「こうし」、「かっし」、「きのえね」と読みます。 暦の上で登場する甲子(きのえね)は、60個ある干支(えと)の一番はじめにあたるもので 特に縁起が良く、60年に一度訪れる甲子の年は「吉祥年」と呼ばれる大吉の年とされています。 阪神甲子園球場の誕生した年は1924年。そう、この年がまさに「きのえね」の年だったんです! 甲子園のように、甲子にあやかった名前を時折目にします。あなたの街でもこの "甲子"を探してみると結構見つかるかもしれません。 ちなみに、次の甲子の年はちょっと先の2044年になります。