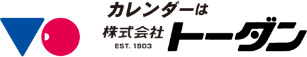冠婚葬祭のしおり
くらしの情報
冠婚葬祭のしおり
| 類別 『表書き』 |
贈り物の心得 | お返しの心得 |
|---|---|---|
| 年賀 『御年賀』 |
1月1日~7日迄に、女性は15日迄でもよい。年賀は本人が持参し、新年の挨拶と共に渡す。 | お返しは不要だが、子供づれの客には、お年玉を渡す。お年玉の表書きに子供の名前を書いてあげると喜ばれる。 |
| 歳暮 『御歳暮』 |
関東は12月初めからおそくとも中旬ごろ迄。関西は12月13日以降。中元よりやや高価なものを。 正月の準備に役立つ食料品などの実用的なものが喜ばれる。 |
お礼状はすぐ出す。お返しは「御歳暮」として改めて贈る。目上、目下から先にいただいてもあわててお返しはせず、お年賀なり、別の機会をとらえてお礼をする。 |
| 中元 『御中元』 |
7月1日~13日迄。もしおくれた場合は暑中見舞にし、立秋を過ぎたら残着見舞に。変質しやすい食料品はさける。 | お礼状はすぐ出す。お返しとしてでなくこちらも「御中元」とする。目上、目下の場合、御歳暮と同じ。 |
| 結婚祝 『御祝、寿』 |
贈り物は挙式当日は避け、式の1~2ヶ月前から1週間位前迄に届ける。櫛、刃物は避ける。 お祝いが挙式当日になったら、現金を祝儀袋に入れ身内の方に渡す。 |
お返しは披露宴に招待しなかったけれど結婚祝いを寄せた方へ、新婚旅行から帰って1~2週間以後に。 表書き/内祝 |
| 出産祝 『御祝』 |
出産通知を受けてから、1~2週間以内に。持参する際には出産経過をみてから。 | お返しは、お祝いをいただいた方へ出産後1ヶ月以内に。 表書き/内祝 赤ちゃんの名前で贈る。 |
| 初節句 『御祝』 |
女子は3月3日前1週間迄に、男子は5月5日前1週間迄に贈る。お人形など。 | お返しは不要。お赤飯や紅白餅をくばってもよい。 |
| 七五三の祝 『御祝』 |
11月の初めに贈る。靴、子供用ハンドバック、帽子、人形など。 | お返しは不要。晴着を見せにうかがって千歳飴を配る。 |
| 結婚記念日 『御祝』 |
紙婚式(1年目)、銅婚式(7年目)、水晶婚式(15年目)、銀婚式(25年目)、金婚式(50年目)。 相手の方の心にふれる贈り物を。 |
お返しは不要。お祝いのパーティーをひらくのもよい。 |
| 寿賀 『御祝』 |
還暦(61歳)、古稀(70歳)、喜寿(77歳)、米寿(88歳)、相手の方の趣味に関した品を贈る。 ※年齢表記は「数え年」です。 |
自筆の書画を額にしたり、袱紗を特別に染めたりして贈る。いただいた方は長寿にあやかるといわれている。 表書き/内祝 |
| 新築祝 『御祝』 |
新築後半月位に贈る。インテリアは家を見て、その家の主人と相談してから贈る。 | 新居に落ち着いてからくばる。 表書き/内祝 |
| 弔事(仏式) 『御香典、御仏前、御霊前』 |
香典は、とりあえずの弔問、通夜、告別式のいずれの場合に出してもよい。姓は水引下部中央に必ず薄墨で書く。中包みに住所・氏名を。 香典の額は月収の1~3%に。金額は裏面に書く。 |
お返しは香典か供物を供えた方に35日か49日に。形見分けをいただいても、お礼はしない。 表書き/志、忌明 |
| 病気見舞 『御見舞』 |
病状に合わせて贈る。鉢植え、つばきの花は避ける。 | お返しは床上げ後、1週間位に。 表書き/内祝、快気祝 |
| 災害見舞 『御見舞』 |
すぐに役立つ身の周り品、食料品、寝具、現金等を。 | お返しは不要。生活が落ち着いてから御礼状を。 |
| 入園・入学祝 『御祝』 |
入園入学祝は直後に、通園通学に必要な品を贈る。絵本や教育的なおもちゃ、図画セットなどの学用品を。 | お返しは御礼の挨拶程度でよいが気がすまなければ、子供と挨拶に行き、赤飯を配る。 表書き/内祝 |