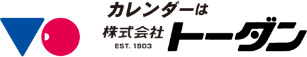五節句
くらしの情報
五節句(ごせっく)
年中行事を行う日のなかでも特に重要とされた日(節日)を節句といい、人日(じんじつ)、上巳(じょうし)、端午(たんご)、七夕(しちせき)、重陽(ちょうよう)の5つがあり、これらを合わせて「五節句」といいます。昔、節句の日には農作業などの仕事を休む習慣があったと言われています。
人日(じんじつ) 1月7日
7番目の占い
中国では年が明けると、1日に鶏、2日に狗(犬)、猪(豚)、羊、牛、馬の順に占いを立て、七日目に人の占いをしました。 その為 1月7日を人日(じんじつ)と呼び、この日に若菜を食べてその生命力で邪気を払う習慣がありました。これが日本に伝わり、 今の七草粥となったのです。ちなみに平安時代、宮中では米、粟、黍(きび)、稗(ひえ)、みの、胡麻、小豆の七種の穀類が入った粥を食べて一年の無病息災を願ったと言われています。
七草粥(ななくさがゆ) 1月7日
七草粥
「せり・なずな・ごぎょう・はこべら・ほとけのざ・すずな・すずしろ」これが現代で言う春の七草です。せり(芹)は セリ科の多年草で、なずな(薺)は原っぱでよく見かけるぺんぺん草のことです。ごぎょう(御形)は母子草の異名、はこべら(繁縷) はハコベ、ほとけのざ(仏の座)はキク科のタビラコの別名、すずな(菘)はかぶで、すずしろ(蘿蔔)は大根です。 現在のようなお粥になったのは室町時代以降と言われています。 では、七草粥を作ってみましょう。
【七草粥を作ろう】
●材料 :米、塩少々、七草適量
1.七草をさっと茹でて水にさらし、固く絞って細かく刻む。

2.米の5~6倍の水をいれ、初めは強火で、吹き出しそうになったら弱火で20~30分炊きます。

3.七草は風味を生かすために火を止める直前に入れます。塩で味をととのえて出来上がり。
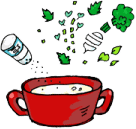
上巳(じょうし) 3月3日 ひな祭
「上巳」とは”桃の節句”のことで、もともとは旧暦3月上旬の巳の日に行われていました。現在では3月3日の「ひな祭」として行事が行われています。
ひな祭のルーツ
ちょっと怖い感じがする右のイラストは形代(かたしろ)といいます。日本では、古来より身にふりかかろうとする災厄や穢れ(けがれ)をこの形代に移して川や海へ流すという習慣がありました。このお祓いの行事と、平安時代頃に宮中や貴族の女の子の間で始まった”ひいな遊び”と言うお人形遊びとが結びついたのが、現在のひな祭のルーツといわれています。ちなみに雛人形の雛(ひな)には「小さな可愛いもの」という意味があります。 当初は質素な形代から始まった人形も、川へ流すものから家に飾るものへと次第に豪華になりました。貴族から庶民へと浸透したのは江戸時代。庶民の経済力が著しく繁栄し、富を得た人々が競って豪華な雛人形を飾るようになりました。壇飾りが生まれたのもこの頃で、現在に至っています。
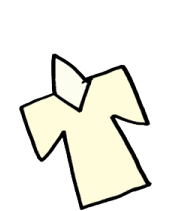
早く片付けないと婚期を逃す?
というのは迷信ですが、もともとのルーツが穢れ(けがれ)を移す身代わりだったことから、いつまでも身近に置くのは良くないと考えられていたのでしょう。「せっかく出したのに、もうしまうの?」なんて面倒くさがらずに、ルーツを知ったからこそ、ひな祭が過ぎたら早めに片付けましょう。
どちらが右?左?決まりはあるの?
現在のひな飾りは関東と関西(特に京都)で配置に違いがあるようです。 日本では昔から向かって右が上位であると考えられていたため、それに合わせて雛人形も右が男雛、左が女雛でした。京都など関西の一部では現在もこのように配置しているのですが、明治以降に一部の皇室の行事に西洋の習慣である「女性は向かって右に位置する」という方式を取り入れた事から、関東では雛人形もそれに合わせて男雛と女雛の位置が逆転したようです。

ひし餅が3色の理由
ひな祭といえば、桃、白、緑の綺麗なひし餅。これらの色にはちゃんと意味があり、 下から新緑の大地を表す緑、純白の雪、桃の花を表すピンクとなります。ちょうどこの季節、雪の下には新緑が芽吹き、桃の花が咲く頃。奥ゆかしい季節の情緒を表現していたのですね。 ちなみにかつて緑にはよもぎを、ピンクにはクチナシの実を入れ、体にもとても良いお餅でした。 菱形なのは、ひしの実ばかり食べていた中国の仙人が長寿であったという話から、それにあやかり菱形になったと言われています。
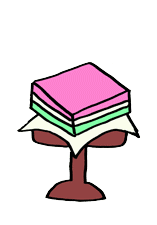
端午(たんご) 5月5日
端午の節句は「女性の節句」?
農家では、五月になると田植えが始まります。 昔は、女性が田植えの主役でした。女性は子供を産むということから、稲の豊作を願って、そういった風習ができたのかもしれません。女性たちは、魔よけとして使われる菖蒲(ショウブ)と蓬(ヨモギ)でつくられた小屋で身を清めてから、田植えを始めるという習慣がありました。これが端午の節句のはじまりです。つまり、女性の節句だったのです。

武士に通じる菖蒲
端午の節句は、鎌倉時代頃から「男の節句」に移行してきました。鎌倉時代の武士は、端午の節句で用いられていた菖蒲(ショウブ)を尚武(武を尊ぶの意)にかけて、これを男の節句としたのです。これが次第に庶民の間にも広がっていきました。

鯉のぼり・いずれは竜となる
端午の節句に飾られる鯉のぼりにも、色々な意味があるんです。中国の故事に「龍門へと続く黄河は、恐ろしいほどの激流で、魚が河を登ろうとしても途中で力尽きてしまうが、鯉だけは川登りを達成でき、最後には竜になる」という話があります。いわゆる「鯉の滝登り」ですね。つまり鯉のぼりは立身出世を願い、飾られたというわけです。また「まな板の鯉」ということわざは、「他人の意のままになる以外に方法のない状態」という意味で使われていますが、鯉は一度水揚げされてから、まな板に活きたまま乗せられても、ひとはねするだけで後は微動だにしないということから、窮地に立たされても慌てずにいる様子を表し、「潔さ」「武士道」に通じるともされてきました。
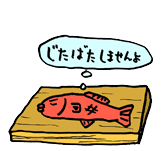
柏餅に葉っぱが巻かれている理由
"端午の節句"に欠かせない食べ物と言えば柏餅!柏餅は、あんこ入りのお餅に柏の葉が巻かれている和菓子。でも、柏餅にはどうして柏の葉が巻かれているのでしょう?これは"げんかつぎ"なのだそうです。柏の葉は「若い葉が出ないと古い葉が落ちない」ことから「子孫がとぎれない」とされ、柏の葉が巻かれるようになったようです。柏餅は、子孫繁栄の願いが込められた縁起物だったんです。
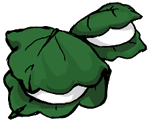
葉っぱの巻き方を見れば中身がわかる!
実は柏餅の葉の巻き方は、中に入っているあんこの種類によって変えられているんです。小豆あんのときは葉の表を外向きにすることが多く、味噌あんのときは葉の裏を外向きに巻いてあるようです。お店で買うときに注意して見てみるのも面白いかもしれませんね。
しょうぶ湯(しょうぶゆ) 5月5日
しょうぶ湯に入ろう
5月5日が近づくと、八百屋さん、花屋さんで菖蒲を見かけます。 この菖蒲を使って「しょうぶ湯」に入ってみましょう。
※注意!菖蒲湯に使う菖蒲は花菖蒲(アヤメ)とは違います!菖蒲湯に使うのは、サトイモ科の植物です。
1.10本分くらいの菖蒲の葉を用意して、30センチくらいに切って束ねます。
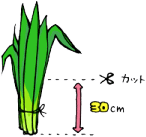
2.浴槽に水を溜め、菖蒲を入れて沸かします。(給湯式の場合、はじめから菖蒲を入れておき、あとからお湯を入れてください)
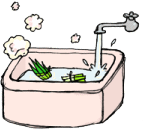
3.熱めの温度に沸かして香りを引き出し、ほどよい温度にさましてから入浴してください。
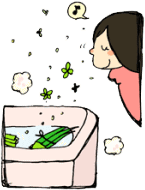
七夕(しちせき・たなばた) 7月7日
七夕のルーツ
満天の星空に広がる天の川。 願いごとを短冊にしたため、織姫と彦星の年に一度の出会いに思いをはせる、ロマンチックな夜・・・。 そう、七夕です。日本の七夕の行事は、色々な説話と行事が組み合わさり出来たものです。ここでは、七夕のルーツと言われている3つのお話を紹介しましょう。
1.年に一度だけの出会い/牽牛星・織女星伝説
これはだれもが知っている織姫と彦星の伝説ですね。天帝の娘である織女と牛飼いの牽牛が、結婚してから全く仕事をしなくなったので、怒った天帝が二人を天の川の両岸に隔ててしまい、年に一度七夕の夜にだけ会うことを許したというお話です。
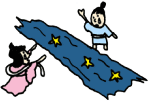
2.短冊に願いをこめて/乞巧奠(きこうでん)の行事
なにやら聞きなれない言葉ですが、これが七夕に願い事をするルーツのようです。天上で機(はた)を織る織女星を神様として、これに祈ることで技芸(裁縫や習字、詩歌など)の上達を祈ったもの。織女星が天にみえるころ、短冊に書いた詩歌やお供え物を捧げたといいます。
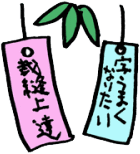
3.先祖の霊に捧げる布を織る女性/棚機つ女(たなばたつめ)
日本には古来より先祖の霊をまつるため、機(はた)織りをして捧げる行事があったといいます。このとき先祖に捧げる布を織る女性を「棚機つ女(たなばたつめ)」と呼んだそうです。「棚機(たなばた)」という名は、「機(はた)」で 織った布を「棚(たな)」に載せて捧げたからだとか、当時の機(はた)は棚(たな)の形をしていたからだとか、いくつか説があるようです。この「たなばたつめ」の説話の伝承によって、「七夕」を「たなばた」と読むようになったというわけです。
8月7日・1ヶ月遅れの仙台七夕
新暦の採用により、「梅雨時の七夕」が生まれてしまいました。そこで地方によっては、「月遅れ」なる方法を考えました。これは新暦と旧暦がちょうど1ヶ月くらいずれているところから、「新暦の行事を1ヶ月ずらす」という方法です。全国的に有名な「仙台七夕祭り」は、この「月遅れ七夕」を採用しています。
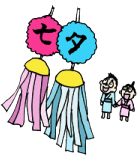
重陽(ちょうよう) 9月9日
菊の節句、九月節句ともいいます。重陽は、易(えき)でいう陽数の極である「九」が重なることで、「重九(ちょうく)」ともいいます。昔の中国では奇数を陽の数としていたので、陽の極である九が重なる9月9日は大変にめでたい日とされました。邪気を祓い長寿を願って菊の花を飾り、酒を酌みかわして祝ったといいます。日本へは平安時代のはじめに伝わり、宮中の儀礼となって「観菊の宴(重陽の宴)」が催されました。また、江戸時代には五節句の中で最も公的な性質を備えた行事となり、武家では菊の花を酒にひたして飲み祝い、民間では栗御飯や粟(あわ)御飯を食べる風習がありました。