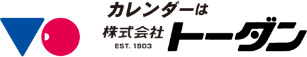四季と暦
こよみの基礎知識
四季と暦
二十四節気(にじゅうしせっき)
太陽の運行を基準にした季節の区分法が二十四節気です。太陰暦(月の運行による暦法)では、暦の日付が太陽の位置とは無関係であるため、暦と実際の春夏秋冬の周期にズレが生じ、農耕にとって大変不便でした。そのため古代中国では、気候の推移を正しく知らせるために長い期間をかけて研究し、二十四節気を考え出しました。
二十四節気は暦の上での気候の推移を表す基準点である冬至を計算の起点にし、一太陽年を24等分したものです。現在は太陽が春分点から黄経上を15度移動するごとに、一節気を進めています。これにより正しい季節がわかるようになり、農作業において大変便利になりました。もともとの発祥は中国ですが、日本においても季節の変化を示すものとして非常に便利だったため、長い間日本の風土に根付いてきました。
雑節(ざっせつ)
二十四節気・五節句などのほかに、それらを補足し、1年間の季節の移り変わりをより的確につかむために重要視されてきたのが雑節です。9つある雑節のどれもが、日本人の長い生活経験から生まれたもので、農業や日常生活の目安として暦に定着してきました。
七十二候(しちじゅうにこう)
七十二候は、ほぼ5日ごとの気象や動植物などの季節変化を示したものです。二十四節気が、ほぼ15日ごとの季節の変化を知らせてくれるのに対し、七十二候はさらにその3分の1の短い期間に区切っているので、より詳しい自然の移り変わりを教えてくれます。
日本では江戸時代の初期まで、古代中国から伝わった七十二候をそのまま使っていましたが、貞享改暦(1685年)のとき、渋川春海によって日本の気候や風土に合うように修正が加えられました。