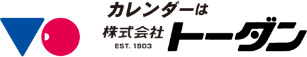雑節
こよみの基礎知識
雑節 一覧

節分(せつぶん)
立春の前日、2月3日頃
旧暦では立春から1年がはじまるという思想をとっています。立春の前日が節分なので、この日は1年の最後と考えられ、邪気を祓い幸せを願う様々な行事が行われてきました。一般的に行われる、豆まきをして鬼を追い出す風習は、中国から伝わったものです。
恵方巻き(えほうまき)
節分の日に食べる太~い巻き寿司。あれってなあに?
それは“恵方巻き”です。近年節分の時期にコンビニエンス・ストアやスーパーで見かける、あの太巻き寿司のことです。 これを節分の日に、ちょっと変わった食べ方で食べます。
節分に食べるワケ
恵方巻きを食べるのは立春の前日、節分の日です。旧暦では立春から新しい年がはじまるとされ、2月の節分は文字通り「年(節)の分かれ目」にあたる日で、年が変わると東西南北にいた神様たちがそれぞれの方位へ遊行します。その中で、歳徳神(としとくじん)という福徳の神様が在位する方位を、“恵方”と呼びます。この“恵方”が、全ての事によしとされる一番の吉方位で、その“恵方”に向かい、一年の幸福を願いながら食べる太巻き寿司。それが“恵方巻き”です。
発祥はどこ?
江戸末期から明治初期にかけて大阪・船場から発祥したといわれています。全国にひろがるきっかけになったのは、1989年に広島のセブンイレブンが販売してヒットしたことからのようです。
これが恵方巻きだ!
その形から食べ方にいたるまで、様々な縁起を担いだ仕様になっています。
地域によって個性もいろいろですが、一部をご紹介しましょう。
・幸福いっぱいの太巻き寿司
中身の具材は、玉子・おぼろ・椎茸・かんぴょう・高野豆腐・三つ葉・すし飯の7種。
これは七福神にあやかっています。それらをぐるぐると巻いて作られることから、「福を巻き込む」との意味もこめられています。
また、普通の巻き寿司のように切らずに まるまるひと巻きなのは、「縁を切らないように」との願いからなのです。
フシギな食べ方
1、 恵方巻きを用意する(くれぐれも切らずに!)
2、 その年の恵方を向く(一年の幸福を願って…)
3、福が逃げないように無言で食べきる(かぶりつきましょう)
豆まき(まめまき)
鬼は外!福は内!
節分とはその名の通り、冬から春への季節の分かれ目です。昔は立春が一年の始まりとされ、その前日の節分にさまざまな年越し行事が行われていました。新年を迎えるにあたり病気などの災いをもたらす鬼を、穀物の霊的な力が宿る大豆をまいて退治するのが豆まきです。
鬼もビックリ!!
北海道では大豆の代わりに落花生をまきます。落花生なら殻がついているため床に落ちても中身はきれいだし、大きいので拾い集めるのもカンタン。北海道に限らずいろいろな地域で取り入れられているみたいですよ。
豆だけじゃないぜ
鬼を追い払うのは豆だけではありません。玄関先などに、魚の頭が刺さった枝を見ませんか?これは「やいかがし」といって、焼いた鰯の匂いと、トゲのある柊で鬼を追い払うというおまじないなんです。怖~い鬼ですが、鰯の匂いが大の苦手なんですよ。
彼岸(ひがん)
年2回ある。春分・秋分の前後3日を含む7日間
彼岸は日本独特のもので、もともと仏教における祭事でした。先祖の霊を供養し、墓参りをする習慣があります。彼岸の頃になると寒暑ともにようやく峠を越して、「暑さ寒さも彼岸まで」の言葉通りに過ごしやすい気候になってきます。彼岸は季節の変わり目でもあります。
ぼたもちとおはぎの違いは?
お彼岸にお供えされる「ぼたもち」と「おはぎ」ですが、その違いを知っていますか?
実はほとんど同じものなんです。
春はぼたもち、秋はおはぎと季節によって名前が変わります。
漢字で書くと一目瞭然、ぼたもちは「牡丹もち」、おはぎは「お萩」。春の牡丹、秋の萩の花に見立ててこのように呼ばれています。
でも、元々は違いがありました。それはあんの種類です。
あんの材料の小豆は秋に収穫されます。採れたて旬の小豆は皮も柔らかいので粒あんに、冬を越し皮が硬くなってしまった春にはこしあんに使われます。つまり、こしあんのものがぼたもち、粒あんのものがおはぎでした。
最近では品種改良や保存方法の進歩により、一年中皮の柔らかい小豆を利用することができるようになったことで、あまり区別をつけなくなってきたようです。
社日(しゃにち)
年2回ある。春分・秋分に最も近い戊(つちのえ)の日
彼岸は仏事に関係しますが、社日は神事に関係します。「社」は生まれた土地の守護神である「産土神(うぶすながみ)」のことで、この日に産土神に参拝し、春なら五穀の種を供えて豊作を祈り、秋は初穂を供えて収穫のお礼参りをします。
八十八夜(はちじゅうはちや)
立春から88日目、5月2日頃
もうすぐ立夏という頃ですが、遅霜の時期でもあります。農家にとってはこの遅霜が最も怖く、新芽を出して生長しつつある作物に与える害が非常に大きいことから、注意を喚起するため特別に暦に記載されました。農事上の重要な節目と考えられ、茶摘み、苗代の籾蒔きなどの目安にもされています。
入梅(にゅうばい)
6月11日頃
現在は、気象学上で太陽が黄経80度を通過した日を入梅としています。ただし入梅は暦の上の話であり、気象庁でも「梅雨入り宣言」を出す日を迷うほどです。日本のように南北に長い国土では、年や地方によって時期が違うのは当然のことなのです。しかし、昔から農家にとって、梅雨入りを知ることは田植えをするために重要でした。なお、入梅の語源については、梅の実が熟する頃に雨季に入るところからきています。
半夏生(はんげしょう)
7月2日頃
七十二候のひとつであると同時に、雑節のひとつにも数えられます。半夏生は梅雨の終期にあたり、農家ではこの日までに田植えを済ませ、どんなに気候不順な年でも、この日以降には田植えをしないという習慣がありました。八十八夜とともに、江戸時代では農家にとって重要な雑節でした。なお「半夏」とは水辺に生える「からすびしゃく」という多年草のことです。半夏生とは、それが生える時期ということになります。
土用(どよう)
4回ある。立春、立夏、立秋、立冬の前の18日間
本来は二十四節気の立春・立夏・立秋・立冬の前の18日間を土用といい、1年に4回ありますが、現在一般的には立秋前の夏の土用を指すようになりました。またその頃は猛暑の時季で、昔から食養生の習わしがありました。土用の丑の日には、うなぎを食べる習慣がありますが、それは暑中の健康管理につながっています。
土用の丑(どようのうし)
夏の土用
年に4回、立春、立夏、立秋、立冬の前の18日間のことを土用といいます。 土用は季節の変わり目にあたり、その中でも、夏の土用(立秋までの18日間)は暑さ極まり、体調を崩しやすい時期になります。
体調管理には「う」のつく食べ物
そんな土用の丑の日には、うどん、牛、馬、梅干し、うさぎなど、「う」のつく食べ物を食べるのが良いという風習があったんです。特にうなぎや肉類は、栄養豊富で疲労回復になるので夏バテ防止にもなっていたようです。
「土用の丑」と言えば「うなぎ」
江戸時代に、繁盛していないうなぎ屋に、多彩な分野で活躍した天才・平賀源内が「今日は丑」と看板を出すようにアドバイスしました。するとどうでしょう。この言葉に江戸の町人が引きつけられ、店が大繁盛することになりました。
他のうなぎ屋も、次々とこの文句を真似るようになり、いつしか、「土用の丑と言えばうなぎ」 となったわけです。
東京「うなぎ丼」vs関西「まむし」
「まむし」とは、大阪で「うなぎ丼」のことです。うなぎをご飯にまぶすから「まむし」と言われているそうです。
その「うなぎ丼」と「まむし」 では、うなぎの調理法に大きな違いがあります。武士の町であった東京では、うなぎの腹を切ることが切腹に通じると嫌い、背ざきにします。一方、それにこだわらない大阪では、手早い腹ざきです。
また、東京では、頭を落として切り身にしたうなぎを、まず白焼きしてから蒸し、また焼きます。大阪では頭をつけたまま6匹ばかりのうなぎに串を打ち素焼きにし、たれをつけながら炭火でじっくり焼き上げます。このため、蒸して脂を抜いた東京風かば焼きはあっさりと柔らかく、関西風は皮は固いが脂肪も残り、そのものの旨みが味わえるのです。
二百十日(にひゃくとおか)
立春から210日目、9月1日頃
この時期は稲の開花期にあたり、台風の襲来を警戒するために暦に記載されました。昔から旧八朔(旧暦8月1日)や二百二十日とともに、天候の悪い三大厄日として恐れられてきた日です。八十八夜や入梅と同様に、長年の経験に基づいて記載された日本独特の雑節です。
二百二十日(にひゃくはつか)
立春から220日目、9月11日頃
二百十日と同じ意味を持つ雑節のひとつで、台風の襲来を警戒するために暦に記載されました。