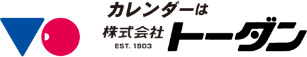二十四節気
こよみの基礎知識
二十四節気 一覧

1月 小寒 大寒
![]() 小寒 (しょうかん)
小寒 (しょうかん)
一年中で一番寒い時期である「寒」の前半に当たり、各地で雪が降り、池や沼湖が氷結する。小寒に入って4日目を「寒四郎」といい、麦の厄日とされた。また9日目を「寒九」といいこの日に雨が降ると豊作とされた。
![]() 大寒 (だいかん)
大寒 (だいかん)
「寒」の後半に当たり、極寒の時期で、各地で最低気温を記録する。昔からこの頃に汲んだ水は長持ちするといわれ、酒の仕込みが行われる。また、寒参りや寒稽古などで寒さを克服する。大寒の最後の日が節分である。
2月 立春 雨水
![]() 立春(りっしゅん)
立春(りっしゅん)
春の始めとはいえ寒さは厳しい。しかし、立春を過ぎると昼が少し延びたと感じられるようになり、気温も僅かずつ上昇する。立春が旧暦の12月の内にあると「年内立春」といい、1月にあるのを「新年立春」という。
![]() 雨水(うすい)
雨水(うすい)
いままで降り積った雪や氷が解け始め、また降る雪も雨に変わる頃である。気温はさらに上昇して、木々の蕾もふくらみを増してくる。水も温み、農家はそろそろ春の農作業の準備をし始める。
3月 啓蟄 春分
![]() 啓蟄(けいちつ)
啓蟄(けいちつ)
冬の間地中に巣ごもりしていた虫が冬眠から覚めて、戸を啓(ひら)くという意味である。さまざまな虫が地上に姿を現わす。中国は漢時代に「啓」が第6代皇帝の諱(いみな)であったため、驚蟄と改められた。
![]() 春分(しゅんぶん)
春分(しゅんぶん)
立春から始まった春の季節のちょうど真中に当たる。この日、日出から日没までの昼と、日没から日出までの夜の時間が等しく、また太陽は真東から昇り、真西に沈む。寒さもようやく収まる。
4月 清明 穀雨
![]() 清明(せいめい)
清明(せいめい)
万物が「清浄明潔」であるという意味で名付けられた。各地で桜を始め、さまざまな花が咲き乱れ、一年で最も心の浮き立つ頃となり、人々は野外へ出て春の陽光の下で楽しむ時期である。
![]() 穀雨(こくう)
穀雨(こくう)
穀物の生育を助ける春雨がしきりに降る頃である。もともとは冬に播いた麦類を育てる雨という意味であったが、麦類に限らずあらゆる作物にとって大切な雨が降る。卯の花の咲く頃で「うのはなくだし」ともいう。
5月 立夏 小満
![]() 立夏(りっか)
立夏(りっか)
二十四節気の上で夏の最初となる。例年八十八夜の3、4日後に当たり、野山は新緑にあふれ、茶摘みの適期となる。行楽のシーズンでもあるが、農家は農作業に忙しくなり、田植が始まる地方もある。
![]() 小満(しょうまん)
小満(しょうまん)
万物が次第に長じて、天地に満ち始める頃である。野山の緑はいちだんと濃さを増し、麦の穂が生長して稔りの時が近づく。南の方から梅雨が始まり、多くの地方で田に水が張られて田植が始まる。
6月 芒種 夏至
![]() 芒種(ぼうしゅ)
芒種(ぼうしゅ)
芒とは麦や稲などにある禾(のぎ)のことで、麦は麦秋を迎えて刈取りが始まり、稲は田植を終えて、すくすくと生長し始める。梅の実が黄色く色づき、ほとんどの地方が梅雨に入る。
![]() 夏至(げし)
夏至(げし)
北半球では昼が最も長く、夜は最も短い。緯度の高い地方では太陽はほとんど沈まない。ただし、日本ではまだ梅雨が続き、日照時間が少ないため、気温は比較的低めである。
7月 小暑 大暑
![]() 小暑(しょうしょ)
小暑(しょうしょ)
そろそろ各地で梅雨が明ける。この頃強い雨で被害が出ることがある。気温は次第に高くなり、蒸し暑い日が続くようになる。これから1ヶ月間が暑中で、小暑の終わり頃から夏の土用に入る。
![]() 大暑(たいしょ)
大暑(たいしょ)
梅雨が明けて太陽がギラギラと照りつける一年で一番暑い時期である。夏の土用に当たり、この頃の庚(かのえ)の日は三伏といって、火の気が最も盛んな厄日とされる。年間の最高気温はこの頃観測されることが多い。
8月 立秋 処暑
![]() 立秋(りっしゅう)
立秋(りっしゅう)
二十四節気の上で秋の最初とされる。実際には大暑に続いて暑い時期で、立秋の語に違和感を持つ場合が多い。旧暦では七夕や盆はこの頃の行事なので、澄んだ夜空に星や月を仰いで催された。
![]() 処暑(しょしょ)
処暑(しょしょ)
暑さが止むという意味である。30℃を超える真夏日や、寝苦しい熱帯夜が少なくなる。処暑の8日から9日後は二百十日で、台風シーズンの到来を告げる。稲に穂が出て、最も気象に注意が必要な時期となる。
9月 白露 秋分
![]() 白露(はくろ)
白露(はくろ)
朝夕少し涼しくなり、草木の葉に白い露が宿るようになる。まだ気温の高い日もあるが、秋草の花が咲き、秋がゆっくりと近づいたと感じられる。草むらでは虫の音が涼しさを一層濃くしている。
![]() 秋分(しゅうぶん)
秋分(しゅうぶん)
秋分には春分と同じく昼と夜の長さが等しくなる。また、秋分の日秋の彼岸の中日で、暑さもようやく収まり、しのぎやすい時期となり、秋の味覚が食卓を賑わせてくれる。中秋の名月もこの頃である。
10月 寒露 霜降
![]() 寒露(かんろ)
寒露(かんろ)
朝夕の冷え込みはいちだんと増し、秋草の葉に冷たい露がつくようになる。山野の風情も秋色を増し、稲はたわわに稔り、黄金の波を打つようになる。収穫を感謝する秋祭りの時期である。
![]() 霜降(そうこう)
霜降(そうこう)
北国や山間部では霜が降りるようになる。平野部でも早霜の害を受けることがあるので用心が必要である。秋の収穫のたけなわで、農家は多忙を極める。紅葉前線は次第に南下し始める。
11月 立冬 小雪
![]() 立冬(りっとう)
立冬(りっとう)
二十四節気の上で冬の最初。次第に太陽の光が弱くなり、また昼が短くなったことを感じるようになる。冬の到来を知らせる「木枯し1号」が吹いて、落葉を払う。時雨が降って、しみじみとした気分となる。
![]() 小雪(しょうせつ)
小雪(しょうせつ)
北国や山間部から初雪の便りを聞くようになる。関東以西の平野部では、まだしばらく降雪はない。収穫を終えて、ゆったりした気分で、最後の紅葉狩りを楽しむこともある。旧暦10月の暖かい日を小春日和という。
12月 大雪 冬至
![]() 大雪(たいせつ)
大雪(たいせつ)
平野部では「大雪」の語には縁遠いが、地方によっては深雪に埋もれたり、厚い氷に閉ざされ始める。スキー場開きのニュースもちらほらと聞かれるようになる。高い山の冠雪を見て冬の到来が実感される。
![]() 冬至(とうじ)
冬至(とうじ)
一年で一番昼が短く、夜が長い日。この日を境に少しずつ昼が長くなる。次第に弱まってきた太陽の陽の気が、この日から再び強くなるところから「一陽来復」を祝う。南瓜を食べ、柚子湯に入って太陽の気を摂取する。